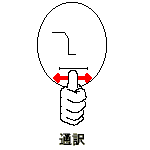身体障害者福祉概論
障害者基本法
障害者基本法とは行政が身障者の為年間計画を進める法案である
しかし
行政(国)が行う法案内容では結果が反映されていないため
新たに
報告を行う義務を追加した
立案前に地域の障害者の声を反映させる
情報の保証
施設などの建設やその他のものを計画するさいに障害者の意見を聞かなければならない
今までは聞くこともなく障害者の立場を無視していた
現に私の住んでいる町でも大きな施設なのに何の配慮もなされていない施設が数多きある
車椅子ではのぼることの出来ない急なスロープ
車椅子同士が離合するどころか、大人が2人立つと通路がふさがってしまう通路の奥にある車椅子専用のトイレ
本当に何も考えず作られたような、それが公共の施設であってもである
新長期計画・障害者プラン
なぜ「障害者プラン」ではなく「新長期計画」とついているのか?
昭和56年(1981年)に国連が発表した
障害者年
(これから10年にわたり障害者のために良い社会作りを目指そうというもの)
これに日本も賛同し10年計画を作成した
これが長期計画である
しかし10年経過した後でも結果は良く放っておらず
さらに計画を10年延長した
これが新長期計画である
この新長期計画・障害者プランの中に
ノーマライゼーション7年戦略という物がある
ゴールドプラン(高齢者)
エンゼルプラン(児童)
障害者プラン(身障者)
上記の3項目障害者プランを支える為
リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえ
次の7つの視点から施策の重点的な推進を図った
1、地域でともに生活をする為に
障害のある人々が社会の構成員として地域の中でともに生活を送れるよう
住まい、働く場・活動の場や必要な保険福祉サービスなどが
的確に提供される体制の確立を目指す
2、社会的自立を促進する為に
障害の特性に応じたきめ細かい教育体制の確保及び障害者がその適正と
能力に応じて可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加できるような
施設の展開を目指す
3、バリアフリー化を促進する為に
障害者の活動の場を広げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていく為
道路、駅、建物など生活環境面での物理的な障壁の除去への
積極的な取り組みを行う
4、生活の質(QOL)の向上をを目指して
障害者のコミュニケーション、文化活動など自己表現や社会参加を
通じた生活の質的向上を計る為、先端技術を活用しつつ実用的な
福祉用具や情報処理機器の開発普及等を推進する
5、安全な暮らしを確保する為に
災害弱者と言われる障害者を災害や犯罪から守る為、地域の防犯・
防災ネットワークや緊急通報システムの構築、災害を防ぐ為の基盤作りを
推進していく
6、心のバリアを取り除く為に
ボランティア活動等を通じた障害者との交流、様々な機会を通じた啓発・
広報の展開等による障害及び障害者についての国民の理解の推進を図る
7、我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
我が国の障害者施設で集積されたノウハウの移転や施設推進の為の
経済的支援を行うとともに、各国の障害者や障害福祉従事者との交流を
推進させる
このプランも平成6年に作られた計画であり平成14年(2002年)には終了予定である
身体障害者福祉法
身体障害者とは
ケガや病気などで身体に支障をきたした者がこれ以上治らないと医者から
判断された時に身体障害者と判断される
厚生省がお膳立てをし、行政(市町村)が企画計画を行う
障害者社会参加促進事業(昭和45年)
<S45年は手話通訳者が必要法案によって決定された年でもある>
障害者の明るい暮らし促進事業
(メニュー事業とも云う)
32項目(1500万円予算)
この予算の中から都道府県がどれを行うか決めた後実行するために
(メニューから選ぶようにして決定する為)
メニュー事業と呼ばれる
身体に障害があるので社会参加できない
目的として
身体に障害がある人も社会参加できるようにボランティアなどを設置する
ろう者にはコミュニケーション手段として手話養成を行う
<福祉関係は8項目あるがその中の3項目は手話に関するものである>
1、手話奉仕員養成
2、手話奉仕員派遣
3、手話通訳者設置
(設置とは手話通訳者を必要機関に常駐させること)
社会福祉法
手話通訳養成
手話通訳派遣
上記2項目は法律によって実行される
手話通訳者の義務
秘密厳守
(個人に関することは決してなん人にも漏らしてはいけない)
モラル
(自分の誤り、過ちを訂正し報告できる人)
(自分の役割を理解する)
社会的信用を受ける
(手話技術の完成度、誤った手話を使わない)
|
間違いやすい表現
<食前>
食前とは食べる前のこと
食べる前とは
食べる「現在」
前「過去」
「食べる」「過去」=<食前>
<食後>
食後とは食べた後のこと
食べた後とは
食べる「現在」
後「未来」
「食べる」[未来」=<食後>
関連手話
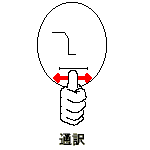
|
 ホームページの「H」を表すのは熊本独特な表現なのかな?^^;
ホームページの「H」を表すのは熊本独特な表現なのかな?^^;